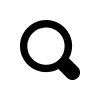事業用(自家用)電気工作物について
はじめにご一読ください。
自家用電気工作物を設置するみなさまへ
事業用(自家用)電気工作物とは
電気工作物の定義
「電気工作物」とは発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために 設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいう。ただし、政令によって鉄道車両、船舶、自動車等に設置される工作物(これ らの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を 供給するためのものを除く。)及び航空機に設置される工作物並びに電圧30ボ ルト未満の電気的設備(電圧30ボルト以上の電気設備と電気的に接続されてい るものを除く。)は除かれる。
自家用電気工作物の範囲
- 600ボルトを超える電圧で受電するもの。
- 構外にわたる電線路を有するもの。
- 次の自家用発電設備(非常用予備発電装置を含む。)を有するもの。
- 太陽電池発電設備であって出力50キロワット以上のもの
- 風力発電設備であって出力20キロワット以上のもの
- 水力発電設備であって出力20キロワット以上のもの又はダムを伴うもの
- 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10キロワット以上のもの
- イ~ニの設備であって、同一の構内に2設備以上が電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が50キロワット以上になるもの
- 火薬類を製造する事業場。
- 鉱山保安規則が適用される鉱山のうち、別に告示するものを有するもの。
用語の説明
-
変電所とは
構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧10万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
-
送電線路とは
発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
-
配電線路とは
発電所、変電所、若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及び、これに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
-
発電所とは
発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に規定する小出力発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法(昭和36年法律第234号)を適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる所をいう。ただし、停電の際に受電と切替えて使用する非常用予備発電設備は需要設備等の付帯設備として取り扱われるので「発電所」とはいわない。
-
需要設備とは
電気を使用するために、工場、ビル等その使用の場所と同一構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に施設されている電気工作物の総合体をいう。
-
需要設備の設置とは
上記需要設備の新設工事をいう。
-
需要設備の変更とは
需要設備を構成する個々の設備又は機器の設置、改造又は取替をいう。
-
改造とは
個々の設備又は機器の構造、強度又は機能を変更する工事をいう。
-
取替とは
個々の設備又は機器を同一の型式、定格又は性能のものと取替える工事をいう。
-
需要設備の最大電力とは
電力会社から受電する電気のみを使用する場合は、契約電力500キロワット以上の需要家は契約電力の値をいい、契約電力500キロワット未満の需要家については契約設備電力の値と実量値をもって決定される契約電力の値のうちいづれか大きい値をいい、自家用発電設備を有する場合は電力会社との契約電力と自家用発電所の最大電力との合計をいう。予備線契約をしている場合又は非常用予備発電設備がある場合は、常時受電と並列できないよう施設されており、「最大電力」には含めない。
関係の手続きについて
自家用電気工作物を設置する者は、電気事業法に基づき、事業場又は設備ごとに電気工作物の工事・維持及び運用の保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任し、策定した保安規程を遵守しなければなりません。
詳しくは、「自家用電気工作物に係る手続のご案内」をご参照ください。
電気主任技術者に係る手続き
自家用電気工作物を設置する者は、事業場又は設備ごとに電気工作物の工事・維持及び運用の保安の監督をさせるため、電気事業法第43条第1項に基づき、電気主任技術者を選任しなければなりません。
電気主任技術者について保安規程に係る手続き
電気事業法第42条に基づき、事業用電気工作物を設置する者は、事業場又は設備ごとに電気工作物の工事・維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を策定し、遵守しなければなりません。
また、保安規程を変更したときは、遅滞なく保安規程の変更届出を提出しなければなりません。
工事計画・使用前安全管理審査に係る手続き
電気事業法施行規則に規定する電気工作物の設置又は変更の工事については、工事着手の30日前までに工事計画届出の提出が必要です。この場合、工事の計画に従って工事が行われたこと及び技術基準に適合するものであることを確認するために、使用前自主検査を実施し、使用前安全管理審査を受審する必要があります。
工事計画・使用前安全管理審査に係る手続きについてその他(名称等変更、地位承継、廃止等)
その他、会社名等の変更や、電気工作物を譲渡した時や廃止した時などにも手続きが必要です。
その他(名称等変更、地位承継、廃止等)の手続きについて電気事業法に係る関係法令について
具体的な手続き方法について
自家用電気工作物を新設する場合
自家用電気工作物を新設する場合、電気事業法に基づき、事業場又は設備ごとに電気工作物の工事・維持及び運用の保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任し、策定した保安規程を遵守しなければなりません。
また、受電電圧1万V以上の需要設備の新設の工事等の場合には、工事着手の30日前までに、工事計画届出の提出が必要です。
自家用電気工作物を売却・購入した場合
【購入者側の手続】
自家用電気工作物を購入した場合は、当該電気工作物の新たな設置者となるため、保安規程を定めるとともに電気主任技術者を選任しなければなりません。
また、電気事業法第48条第1項の規定による届出(工事計画届出)に係る自家用電気工作物を他から購入等して使用する場合は、使用開始届出が必要です。
- 3. 自家用電気工作物使用開始届出書
- 受電電圧1万V以上の需要設備を譲り受けた場合
- ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物を譲り受けた場合
主任技術者を変更した場合
電気主任技術者を変更した場合には、選任解任届出書を提出しなければなりません。
電気保安法人等との保安管理業務の外部委託先を変更した場合
電気保安法人等との保安管理業務の外部委託先を変更した場合には、電気保安管理業務解約届出書の提出と改めて外部委託承認申請書を提出する必要があります。
設置者名・設置者住所、事業場名・事業場住所、代表者名、組織図、主任技術者の執務形態、その他保安規程の記載内容を変更した場合
設置者名・設置者住所、事業場名・事業場住所、代表者名、組織図・主任技術者の執務形態、その他保安規程の記載内容を変更した場合には、保安規程の変更届出を提出してください。
またばい煙(騒音・振動)発生施設を有する場合は、ばい煙発生施設等に関する変更届出書の提出が必要です。
自家用電気工作物を廃止した場合
自家用電気工作物を廃止した場合は、廃止報告書の提出が必要です。
なお、廃止に伴い、PCB含有電気工作物を廃止する場合の手続きはこちらをご覧ください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有電気工作物に係る届出について地位承継(合併・分割)により自家用電気工作物を譲り受けた場合
法人の合併・分割に伴い、自家用電気工作物の設置者たる地位を承継した場合は、事業用電気工作物設置者地位承継届出書の提出が必要です。
既設の自家用電気工作物について変更の工事を行う場合
電気事業法施行規則に規定する電気工作物の設置又は変更の工事については、工事着手の30日前までに工事計画届出の提出が必要です。この場合、工事の計画に従って工事が行われたこと及び技術基準に適合するものであることを確認するために、使用前自主検査を実施し、使用前安全管理審査を受審する必要があります。
電気保安法人・電気管理技術者一覧
電気主任技術者の外部委託について、これまでに当部が自家用電気工作物設置者から提出のあった外部委託承認申請に基づき、委託先としての要件を確認したことがある電気保安法人・電気管理技術者(個人)は次のとおりです。